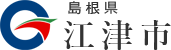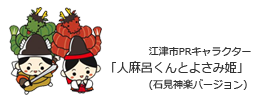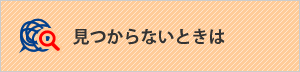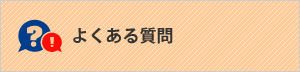本文
万葉の歌碑めぐり
江津と柿本人麻呂と依羅娘子(よさみのおとめ)
江津の万葉は、人麻呂の歌の歌枕と、その妻依羅娘子の出生伝説、さらに万葉の古道を持つところに特色があります。
歌枕は、人麻呂が石見にあって妻に別れる歌と、石見にあって死に臨んで詠んだ歌があります。
これらの歌は、万葉集中の秀歌として、また、人麻呂の代表的な歌として古くから知られています。
人麻呂は晩年に石見の国の国司として赴任し、角の里の依羅娘子と巡り会います。
姫は都野津町の医師井上道益の娘といわれ、この姫の歌は人麻呂の歌と共に万葉集巻2の相聞の部と、挽歌の部に載せられています。
江津に関係のある万葉の歌はこの両人の相聞歌であり、また、挽歌でもあります。
それは相聞歌として、人麻呂が石見の国より妻に別れて上京する時の歌、依羅娘子のそれに答える歌があり、挽歌として人麻呂が石見の国に在って死に臨んで詠んだ歌、依羅娘子が彼の死を悼んで詠んだ歌の3首があります。
即ち石見にあっての歌は総歌数13首、これが江津の万葉の対象となります。
万葉の歌碑めぐり
江津市には万葉の歌碑が6カ所あります。
これは全国にも例を見ないものです。
ここでは、6カ所の歌碑を紹介します。
リンクをクリックすると、それぞれのページへ移動します。
人麻呂終焉の歌
鴨山の 岩根し枕ける われをかも 知らにと妹が 待ちつつあらむ
意訳
鴨山の岩根を枕にして死のうとしているわたくしを、それとは知らずに、妻はわたくしの帰りを待っていることであろうか。
人麻呂の最大の謎は終焉の地が何処か
「柿本人麻呂、石見の國にありて臨死らむとする時、自ら傷みて作る歌一首」として有名な「鴨山の…」がありますが、この歌に詠まれている「鴨山」が石見のどこかが不明で、現在にいたるまで邑智郡美郷町説、益田市説、浜田市説などいろいろあります。
もちろん江津市二宮町説もあります。
依羅娘子の「直の逢ひは逢ひかつましじ…」の歌の中の「石川」も同様に不明です。
鴨山と石川を求めて多くの人々が探求を続けてきました。
この人麻呂の歌の世界を愛するかぎり、終焉の地の探求はさらに続くことでしょう。