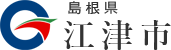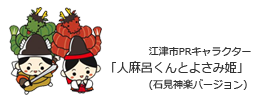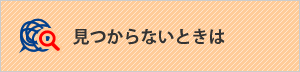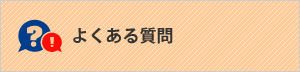本文
選挙に関するQ&A
選挙に関するQ&A
選挙に関することについて、日ごろ質問をいただいたことについて、まとめてみましたのでご活用ください。


選挙権・被選挙権
Q 投票できるのは何歳からですか?
A 日本国民で満18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる選挙権を有します。
Q 選挙権があれば投票できるの?
A 選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。選挙時登録の基準日までに引き続き3カ月以上江津市の住民基本台帳に登録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、江津市で投票できます。また、3カ月に満たない場合は、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。投票できるかどうかわからない場合は、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
Q 最近、市外から引っ越してきたが投票できますか?
A 江津市に転入届を出されてから、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、江津市で投票できます。また、3か月に満たない場合は、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。
投票ができるかかどうかわからない場合は、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
Q 江津市に住んでいない人が、市長に立候補することはできますか?
A 被選挙権は、一定の年齢以上(参議院議員および知事は30歳、その他は25歳)の日本国民が有するものですので、たとえ江津市に住んでいなくても、市長選に立候補することはできます。なお、地方公共団体の議員の場合は、その選挙権を有すること(引き続き3カ月以上江津市に住所があること)が必要となります。
投票
Q 投票時間を教えてください。
A 投票日当日(選挙期日)は、午前7時から午後6時までです。
Q どの投票所に行けば投票できますか?
A 投票所入場券に該当する投票所が記載されていますのでご確認ください。また、投票所一覧からもご覧いただけます。
Q 投票所入場券を紛失したけど投票できますか?
A 投票できます。投票所入場券は、選挙人に対し、選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。投票所入場券を紛失したときや、届いていない場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で受付の係員の申し出てください。
Q 投票日に、投票へ行けないときはどうしたらいいの?
A 投票日に、仕事や旅行などの用事で予定のある人は、期日前投票をご利用ください。選挙の告(公)示日の翌日から投票日前日までの間、江津市では2か所の期日前投票所で投票できます。
- 江津期日前投票所 江津市職員会館 午前8時30分~午後8時まで
- 桜江期日前投票所 桜江保健センター(桜江総合センター内) 午前8時30分~午後6時まで
期日前投票期間中は、土曜日・日曜日でも投票できます。
Q 病院に入院(老人ホームに入所)しているがどうしたいいの?
A 都道府県が指定した病院や老人ホームなどの施設で不在者投票ができます。施設側が取りまとめて投票用紙等の請求を行いますので、施設の担当者もしくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
Q 仕事で海外赴任になりました。投票できるの?
A 外国にいても、国政選挙については投票できます。対象となる選挙は、衆議院議員選挙(国民審査含む。)と参議院議員選挙です。この投票制度を「在外投票」といいます。国外で選挙を行うには、江津市の在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を持っていれば、衆議院議員及び参議院議員の選挙で投票することができます。
在外選挙人名簿への登録の申請には、以下の2つの方法があります。
- 出国後に居住している地域を管轄する日本大使館、総領事館等に申請する方法(在外公館申請)
- 出国前に国外への転出届を提出する場合に、江津市の窓口で申請する方法(出国時申請)
在外選挙人制度<外部リンク>
Q 身体が不自由で投票所に行くことができません。
A 郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がいまたは要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。この制度を利用するためには、あらかじめ市の選挙管理委員会に申請を行い、一定の障がい等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
Q 自分で投票用紙に記入することができない場合、家族が代筆することはできるの?
A 家族であっても代筆はできません。受付で代理投票の申し出をしてください。係員がご本人に付き添い、誰に投票するか意志確認をした後に、ご本人に代わって記入します。
Q 投票所に投票をしない付き添い人も一緒に入れるの?
A 原則として、投票をしない方の立ち入りは認められません。ただし、投票をする方に同伴する子ども(満18歳未満)は投票所に入ることができます。
車椅子をご利用の人・けがをしていて付き添いが必要な人は、投票所の係員が対応します。
Q 遠方からの出張で、江津市に滞在しているが、どうすれば投票できるの?
A 江津市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、仕事や旅行などで、選挙期間中、江津市に滞在している場合は、選挙人名簿に登録されている市区町村に不在者投票の申請を行い、投票用紙を請求すれば、滞在先の江津市選挙管理委員会で不在者投票ができます。
Q 投票所内で気をつけることは?
A 次の3つの行動に気をつけてください。
- 投票所内で、他の人の投票に干渉したり、特定の候補者への投票を呼びかけたりすることは禁じられています。
- 投票用紙は、投票箱に入れなければならないと、公職選挙法で定められています。 投票用紙を投票所から勝手に持ち出すことはできません。
- 投票所内でのスマートフォン等による撮影は、投票所の秩序保持を定めた公職選挙法に違反するおそれがあります。 また、他の有権者の秘密保持のためにも,撮影はご遠慮ください。
開票
Q 無効票とはどんな票ですか?
A どの候補者や政党の票としても扱われないものです。無効票と判断される投票の例は次のとおりです。
- 所定の投票用紙を用いない投票
- 候補者でない者の氏名を書いた投票
- 2人以上の候補者の氏名を書いた投票
- 候補者の氏名のほか、他事を書いた投票
(例)〇〇〇〇さんへ、〇〇〇〇さんガンバレなど - 候補者の氏名を自書しない投票
(注)代理投票は自書ではありませんが有効です。 - どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票
- 白紙投票
- 単なる雑事や記号等を書いた投票
投票所には候補者の氏名などが掲示されています。掲示のとおり投票用紙へ正確に記入してください。
選挙運動と政治活動
Q 選挙運動と政治活動の違い何ですか?
A 政治活動とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動をいいます。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
Q 選挙運動はいつからできるの?
A 選挙運動は、告(公)示日に立候補届出が受理されてから投票日前日まですることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
Q 候補者が行える選挙運動は?
A 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
Q 候補者がやってはいけない選挙運動は?
A 次のような選挙運動は禁止されています。
戸別訪問(公選法第138条)
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
買収(公選法第221条)
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
署名運動(公選法第138条の2)
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
飲食物の提供(公選法第139条)
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
あいさつを目的とする有料広告(公選法第152条)
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
気勢を張る行為(公選法第140条)
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
選挙後のあいさつ行為(公選法第178条)
誰であっても、選挙後に当選または落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。
Q インターネット等での選挙運動はできると思うが、禁止されていることは何か?
A インターネットを利用した選挙運動については、特に次の点に注意してください。
- 年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。
- インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は告(公)示日に立候補の届出がされてから投票日の前日までしかすることができません。
- 電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限られます。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。
- 選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。
インターネット選挙運動<外部リンク>
寄附
Q 禁止されている寄附って?
A 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人をいいます。)は、選挙区内の人に対して寄附をすることは、その時期や名義いかんを問わず禁止されています。主なものは次のとおりです。
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結構祝い
- 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
- 葬式の花輪や供花
- 入学祝い、卒業祝い
- お中元やお歳暮
- 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- 氏子や檀家になっている社寺の修繕等に対する寄進やお賽銭など
ただし、次のものは罰則の対象から除外されています。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀(物品を含む。)
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典(金銭のみ。)
詳しくは、政治家が寄附をする事は禁止されていますをご覧ください。
Q 政治家は選挙区内にある者に対して、時候のあいさつ状を出せるの?
A 年賀状、暑中見舞状、残暑見舞状、寒中見舞状、クリスマスカード、喪中欠礼葉書、年賀電報などは禁止されています。(答礼のため自書によるものは除く。)
その他
Q 選挙時に発行される「選挙公報」はどこで手に入れることができますか。
A 告(公)示日以降にかわらばんと同じ方法で、各家庭に順次配布します。市役所、桜江支所、各地域コミュニティ交流センターなどに備えつけておりますのでご利用ください。なお、投票所入場券のQrコードからも見ることができます。