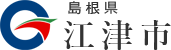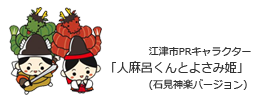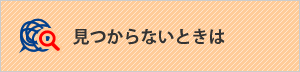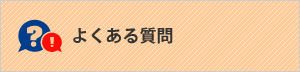本文
第三者(利害関係人)による住民票の交付の申出や戸籍証明書等の請求
概要
法人等の第三者が住民票の交付の申出や戸籍の証明の請求をできるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しの交付を申し出る場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票の写しの交付を申し出る場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
法人等の場合の請求方法
次の書類などをご用意していただき、市役所窓口または郵送で提出してください。
- 申出書または請求書(様式任意)
- 誓約書
「今回取得する住民票、戸籍等は、使用目的以外には使用しないことを誓約します。」など
※申請書に記入してもかまいません。 - 契約書写しなど疎明資料
- 法人の確認書類
代表者の資格を証する登記事項証明書の原本(全部事項証明書、代表者事項証明書など発行から3か月以内のもの) - 担当者の本人確認資料
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)に加え、法人の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証または在職証明書もしくは代表者作成の委任状
※郵送の場合は写し - 手数料(郵送の場合は郵便定額小為替)
手数料一覧はこちら - 郵送の場合のみ:返送先住所を記入した返信用封筒及び切手
※法人の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料(名刺は該当しません。代表者の資格証明書や社員証で確認できる場合は不要です。)
疎明資料について
申出書または請求者(債権者など)と対象者(債務者など)が確認できる契約書の写し(契約日・住所・氏名・生年月日等)で契約者の自署が確認できるもの。
※インターネット申し込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を記載し、法人及び社印を押印し、「契約内容に相違ない」旨を記載してください。
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しまたは、履歴事項証明書が必要です。
債務者の相続人を確定するために請求する場合は、債務者の死亡の記載がある除票の写し
※法定相続人の請求の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等も必要です。
申出書または請求書について
申出書または請求書(様式任意)へ以下の必要事項を記入・押印してください。
- 法人の住所・法人名および代表者氏名・法人の印
- 担当者の住所・氏名・生年月日
- 対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者氏名または対象者の住所・氏名・生年月日
※住民票の場合は本籍・筆頭者が不要 - 必要な証明書の種類と通数
- 具体的な申請理由及び使用目的
使用目的は、「債権回収・債権保全」だけでは曖昧なため権利・義務の「発生原因・内容・証明が必要な理由」について次の例のように具体的に記載してください。請求理由によっては交付できない場合があります。
- 「支払が滞っている債務者と不通になっていることから、債務者の所在確認のため」など
- 「債務者が●年●月●日死亡し相続人を確定するために本籍地入りの除票が必要」
※正しい死亡日の記載が必要 - 「債務者が●年●月●日死亡し相続人を確定するために出生から死亡までの戸籍が必要」など
※理由を証する疎明資料(対象者が死亡の場合は、死亡が記載された除票の写しが必要)
個人の場合の請求方法
次の書類などをご用意していただき、市役所窓口または郵送へ提出してください。
- 市役所窓口の場合:窓口にある「証明交付申請書」に記入
- 郵送の場合:「戸籍証明書等請求書・住民票等郵便請求書」に記入し、返信用封筒とともに郵送
郵便請求について、詳しくは「戸籍証明等(戸籍謄抄本、附票、身分証明書等)の郵便請求」をご確認ください。
記入について
交付申請書または郵便請求書には、以下の必要事項の記入が必要です。
- 請求者の住所・氏名・生年月日
- 対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者氏名
※住民票の場合は本籍・筆頭者が不要、住所・世帯主の記入が必要 - 必要な証明書の種類と通数
- 具体的な申請理由
(例:提出先は○○家庭裁判所であり、請求者は、令和○年○月○日に死亡した○○(名前)の兄であり相続人であるが、弟の遺産についての遺産分割調停の申立に際して添付するため、弟が記載されている戸籍謄本等を提出する必要がある。)
請求の際に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※郵送の場合は写し - 対象者・相手方との関係が分かる疎明資料(親族関係を証明する場合は戸籍で確認できるため不要です)
- 手数料(郵送の場合は郵便定額小為替)
手数料一覧はこちら - 郵送の場合のみ:返送先住所を記入した返信用封筒及び切手
職務上請求について
弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は、受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求でき、有効な統一請求書の利用及び資格証明等の提示が必要となります。
受任している事件または事務に関して、統一請求書に内容を記載していただく必要があります。
対象の戸籍の本籍及び筆頭者が明記されていない場合は、原則請求の受付ができません。