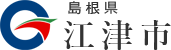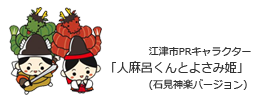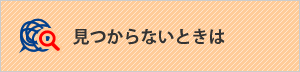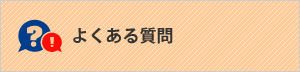本文
ヨシヒコの江津まち歩きツアー 桜江町市山・今田・小田(令和4年5月31日)
「まち歩きマップ」作成までの取り組みを紹介します。
ヨシヒコのまち歩きツアー 桜江町市山・今田・小田
ヨシヒコは思った。
お医者さんから「1日1万歩きなさい」と言われたのに、脇腹が痛くて、最近歩いていなかった。
そうだ、今回は桜江町でまち歩きマップを作って、市民のみなさんに、文化財や道路の名前、観光地などをを中心に桜江町を知ってもらおう!
そして、これをきっかけに脇腹痛からも復活しよう!目指せ1万歩のまち歩き!
スタート
市山地域コミュニティ交流センター(旧市山小学校)から出発です。
まずは施設内にある「大元神楽伝承館」で大元神楽について学びます。
どうやら、昭和初期までは八戸や長谷、木田、谷住郷などの山間部において、神がかりなどが頻繁にあったようです。この周辺はそれらが乏しかったようです。大元神楽は市山出身の民俗学者の牛尾三千夫さんにより、全国的に知られるようになりました。
市道本町古市線
市山地域コミュニティ交流センターを出て、市道本町古市線を八戸川の方面へ歩きます。
今日は天気が良いので、歩きやすいです。みなさん、熱中症には気をつけましょう。
八戸川沿いを進む
県道桜江金城線を左折し、東側方面に進みます。右手には八戸川が流れています。
江尾橋
少し進むと江尾橋があります。ここは県道桜江金城線と県道皆井田江津線が交差しています。
今日はこの橋は渡らず、江の川方面に進みます。
今田水神の大ケヤキ
鮎観橋の手前に「島根県指定天然記念物の今田水神の大ケヤキ」の看板があり、大ケヤキは川の向こうに見えています。
なお、大ケヤキの下には、延宝七年(1679)に灌漑用水路として掘削された跡があります。
鮎観橋
県道桜江金城線から鮎観橋を渡ります。川の底を見ましたが、鮎は見当たりませんでした。
市山城跡
鮎観橋を今田側から見たところです。
市山の町なかの上に山城の市山城跡があります。
今田農道
鮎観橋を越えて今田農道を正面に見ると、直線の道と山の陵線がきれいに見えて、日本の原風景に会うことができます。
この先は歩かずに、右折して市道山手月の夜線へ進みます。
市道山手月の夜線
市道山手月の夜線を長尾方面に進みます。
この集落を含めた今田地区では、日本の中でも珍しい「大めし祭」という神事を過去に行っていました。
地蔵堂
ここに安置してある地蔵は、弘化3年(1846)の洪水で鳥取県の泊浦まで流されて、その後無事に戻ったという逸話があります。
また、一昔前の若者は、結婚式の会場に地蔵を担いで持っていた風習があったそうです。
八重梅様
この付近には、昔の庄屋の家があり、その裏庭には八重梅様と呼ばれる八重咲きの白い神木があります。
昔は、この神木の前を通る時には右の腰にさしていた鎌を左の腰にさし代えないと祟りがあったと伝わっています。
耕地整理記念碑と井戸明君の碑
そのまま道を進むと右手に耕地整理記念碑(左側)と井戸明君の碑(右側)があります。
耕地整理記念碑は正面に「大正元年十二月着手・今田耕地整理記念碑」と書かれています。
井戸明君の碑は芋代官碑と呼ばれており、右の面に「文久二年歳次壬戌」と書かれています。文久2年(1862)に建てられたものと分かります。
大山祇命神社
市道山手月の夜線から宮の谷川を山側へ市道桜江日和線をまっすぐ歩くと、大山祇命神社があります。
善福寺付近
ここは長尾地区です。「ながお」ではなく「なごお」と呼ばれています。
また、この周辺は昔に善福寺というお寺があったと伝わっています。
長尾横穴石室古墳跡地
長尾横穴石室古墳跡地に着きました。8世紀ころの地域の豪族の墳墓と考えられています。
日桜ロード
長尾橋の交差点を市道桜江日和線を山側進み、上り口まできました。
この道は「日桜ロード」と呼ばれていて、凍結による事故防止のため冬期は閉鎖されます。
市道小田長尾線
長尾橋に戻り、橋を越えると、広大な農地が広がります。
先が見えないほどまっすぐな道なので、道はまっすぐだけど心が折れそうです。
小田地区県営ほ場整備事業碑

市道小田長尾線の横に小田地区県営ほ場整備事業の碑があります。碑に書かれている「土と共に生きる」は事業者の強い信念が伝ってきます。
小田八幡宮
県道桜江金城線の横に小田八幡宮があります。ここは大元神楽が重要文化財に指定になって、昭和56年に現地公開を行った場所です。
母抱(ははがかえ)トンネル
母抱(ははがかえ)トンネルまで来ました。
この近くには、『ハアがカアの地蔵』という地蔵があり、むかし母が子どもを抱えたまま八戸川におちたため、その供養として建てられたと言われています。
市山の入り口
トンネルを越えて市山の入り口まで来ました。
左には鮎観橋が見えます。
服部商店
市道市山長谷線の左側に『服部商店』があります。服部商店は、大正6年に『市山興業銀行』として建築され、その後『石州銀行』になり、昭和40年に服部商店になりました。令和2年3月の文化庁の近代遺跡調査報告書(商業・金融業)では、島根県内では、松江のカラコロ工房と服部商店の2つが掲載されています。
ゴール
ゴールの飯尾山八幡宮に到着。
ここまで歩いて、約11,000歩!!1万歩を超えてしまって損した気分だ!
約2時間かかりました。次回こそは、目指せちょうど1万歩!
街歩きマップ(桜江町市山・今田・小田 約11,000歩)