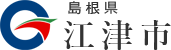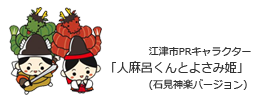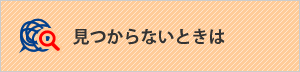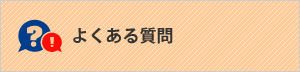本文
予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度について(B類疾病)
予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された人を迅速に救済するものです。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障がいが残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。
厚生労働大臣の認定にあたっては、医療や法律などの専門家で構成された国の審査会で審査されます。
対象となる定期接種
- 高齢者肺炎球菌予防接種
- 高齢者インフルエンザ予防接種
- 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種
給付の対象(請求期限あり)
- 医療費及び医療手当
- 障害年金
- 遺族年金
- 遺族一時金
- 葬祭料
※請求期限は以下のとおりです。
- 医療費:医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年
- 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
- 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年
申請方法
接種に応じて申請に必要な書類や手続きをご案内します。
健康被害を受けたご本人やそのご家族が、予防接種を受けたときに住民登録していた市町村にお問い合わせください。
また、請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があり、必要書類は種類や状況によって変わります。病院に依頼する文書料はすべて自己負担となります。
まずは、ご相談ください。
申請の流れなどの詳しくは、予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>(外部リンク:厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
任意接種による健康被害救済制度
定期接種ではない接種や、決められた医療機関以外で接種したり、接種法定年齢を外れて受けたときには、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。
その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。ただし、救済の対象や支給額などは予防接種法によるものと異なります。
制度の内容については、医薬品副作用健康被害救済制度<外部リンク>(外部リンク:独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご確認ください。