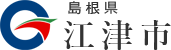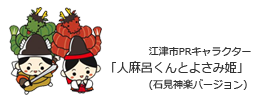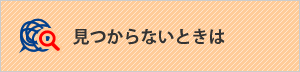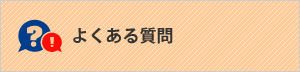本文
ねこの適正飼養
ねこを飼う
私たちは日々、様々な人々と接点を持ちながら生活を営んでいます。ねこを飼うということは、知らないうちにまわりにいろいろな影響を与えます。
適切でない飼養を行うと、近所だけでなく地域の人々に迷惑をかけることにもなってしまいます。
ねこに「畑を荒らされた」「鳴き声がうるさい」「庭にふんや尿をされた」「猫ノミに苦しめられた」「戸や窓があけられない」など、苦情が寄せられることがありますが、これらの苦情のほとんどは、飼い主が飼い方に気をつけることで改善できるものです。
人とねこが幸せに暮らすために、ご近所に迷惑をかけないよう責任をもって飼養しましょう。
飼い主は、ただかわいがるだけでなく、ねこの本能や習性をよく理解し、まわりの人に迷惑をかけないようマナーを守らなければなりません。
そして、家族の一員として終生飼養するという責任感と、命を預かるという自覚を持ちましょう。
飼い主の気をつけること
ねこのトラブルの多くは、ねこを屋外で自由に行動させることに原因があります。飼いねこを屋外に放つことは、自分本位の身勝手な行為と言わざるを得ません。
ねこは屋内飼養が基本です
ねこは生活環境が整っていれば屋内で飼うことができます。
感染症防止、交通事故の防止など、ねこの健康と安全のために、屋内で飼うように努めましょう。特に子ねこの時から屋内のみで飼い、不妊または去勢手術をし、トイレなどを覚えさせれば屋内飼養の定着は容易といわれています。屋内飼養が責任ある飼い主への第一歩と言えます。
屋内で飼うときの注意点
プライベートな縄張りとして、最低限必要な空間を提供する
隠れ場所、食事の場所、トイレの場所、見張り台、遊び場所、休息場所など
しつけと管理を徹底する
定位置での排泄と食事、トイレ砂の管理や清掃、決まった場所で爪とぎをさせる、抜け毛の管理など
ストレスを解消させる
高いところなどの立体的な運動ができること、おもちゃで遊ばせることなど
その他
感染症予防ワクチンの接種、高層住宅等での転落防止など
ねこの本能、習性、行動などを正しく理解し学びましょう
飼い主が、その動物の習性などを勉強するのは当然の義務と言えます。
動物由来感染症などの正しい知識を持ち、ねこと飼い主両方の健康にも注意を払いましょう。ねこにとってごく当たり前の自然な行動が、あなたの住む地域では迷惑な行為になっているかもしれません。
動物が好きな人ばかりではないことを知っておきましょう
あなたの近所にもねこの嫌いな人はいます。嫌いでなくても、アレルギーなどで動物に近寄れない、触れられない人もいるはずです。
ご近所への配慮やコミュニケーションを怠らないようにしましょう。野良ねこにえさを与える行為も慎みましょう。
むやみに野良ねこに餌を与えることはやめましょう
かわいそうな野良ねこにえさを与える優しい気持ちは、人間として大切なことだと思います。
しかし、えさやりによりねこは爆発的に繁殖してしまいます。
また、そのことが、地域住民への悪影響(ふん尿・鳴き声被害)を及ぼすことにつながります。
えさを与えるなら、近隣の理解を得て、食べ残しやふん尿の始末など、きちんとねこの世話をしましょう。
自分の飼いねこは識別できるよう工夫しましょう
万一、屋内から逃げ出しても、あなたの大切なねこがすぐに発見されるのにきっと役に立ちます。屋内飼養でも迷子札をつけましょう。首輪は物に引っ掛かるので、マイクロチップがより安全です。獣医師に相談してみましょう。
飼う前に、10年先を考えて
きちんと飼えば、ねこは10年以上生きます。「10年後も飼い続けていられるか?」、10年後のねこと10年後のあなたのことを考えてから飼いましょう。
動物を捨てることは法律で禁止されています。終生飼養は飼い主の責務です。
飼う前に次のことを確認してみてください
- ねこの生態、習性、病気などの必要な知識はありますか。
- 毎日の世話ができますか。
- 最後まで飼うことができますか。
- 旅行や外出が制限されることを覚悟できますか。
- 予防接種、病気の時の治療費などの経費は大丈夫ですか。
- 繁殖を望まないときには、不妊去勢手術をできますか。
- 飼うことについて家族みんなが納得済みですか。
- ご近所に迷惑がかからないように飼えますか。
- 自分や家族が病気になったときはどうしますか。
- ねこが病気になったり老齢になったとき、介護をすることができますか。
必ず不妊・去勢手術を行いましょう
ねこはとても繁殖力のある動物です。自宅で繁殖させる計画でもない限り、必ず不妊・去勢手術を行いましょう。
- 発情期は年3~4回、1回に2~5匹出産。
- 11ヶ月で成熟。8歳まで産むとして、42匹から多いと140匹も出産!
手術で感染症を防ぎ、発情によるトラブルがなくなります。
手術するメリット
メス、オスともに
生殖器の病気を防ぐ、性格が穏やかになる、屋内飼育が容易、長生きできる。
メス
妊娠・出産に伴う健康上のリスクの回避、発情によりオスがたくさん集まることの回避。
オス
尿スプレー(おしっこをかける行動)、ケンカ、うなり声がかなりの確率でなくなる。
ねこを捨てないで
誰かが拾ってくれるだろうと安易な気持ちで、ねこを捨てないでください。
捨てられたねこは、飢え、病気、交通事故などで不幸な死を迎えるか、野良ねこになってみんなに迷惑をかけることになります。
また、動物を捨てることは動物愛護法違反です。
子ねこが生まれたら、責任をもって、新しい飼い主さんを探してください。飼い始めたら、最後まで責任と愛情をもって飼ってください。
困ったことがあれば、動物病院に相談してみましょう
動物病院(獣医師)はあなたのよきパートナーです。健康面はもちろん、飼い方についても分からないことは相談してみましょう。病気になる前にかかりつけ医をもちましょう。
人とねこが快適に暮らすために
社会的集団を構成する犬と違って、祖先が単独生活をしていたねこをしつけることは非常に困難と言われています。
そのため、人がねこの習性や生態などをよく理解し、うまくねこに合わせていくことが、ねことの快適な生活を送るためのコツです。
今は本やインターネットなどで参考になる情報がたくさんあります。それらを活用し、人にもねこにも快適な住みよい社会をつくっていきましょう。
受動喫煙を防ぎましょう
たばこの副流煙(火のついたたばこの先から出る煙)は、人だけでなく一緒に暮らすペットの健康にも悪影響を与える可能性があります。ねこは特に臭いに敏感なため、想像以上に大きなストレスにつながります。大切な家族であるペットのためにも、近くで喫煙することは控え、換気するなどのご配慮をお願いします。